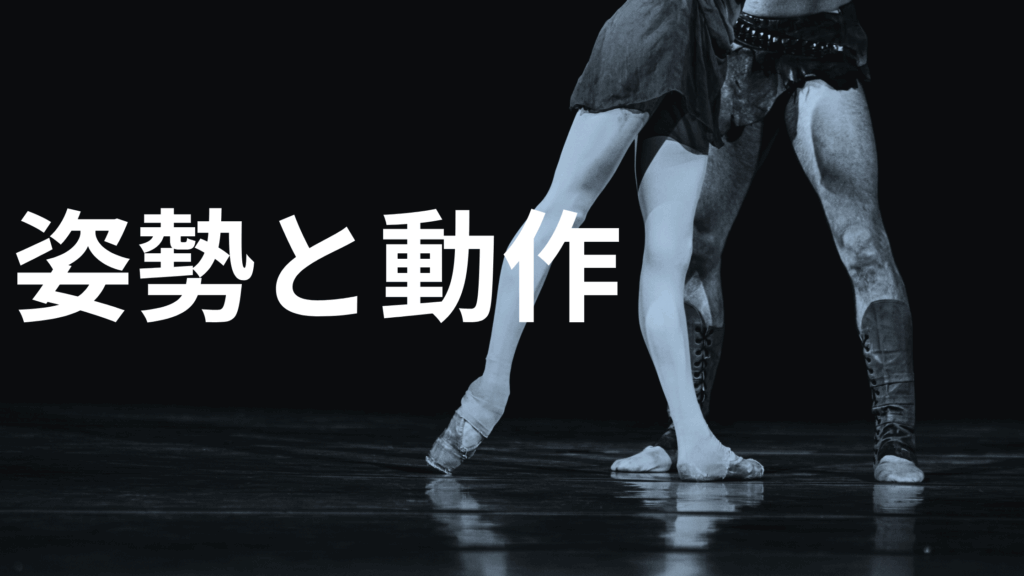
「姿勢が悪いと、動きも悪くなる」
「最近、動きが重い」「反応が鈍い」「以前より疲れやすい」
こうした不調、実は“姿勢”が関係しているかもしれません。
私たちの身体は、重力下で効率よく動くために、姿勢と動作が密接に連動しています。
姿勢が崩れると、からだ全体の連動性が失われ、無駄な力を使ってしまうのです。
でも、ただ背筋を伸ばせばいい──わけではありません。
「姿勢を整えるための“内側の支え”が働いていない」ことが、パフォーマンス低下の本当の原因かもしれません。
“内側の支え”──それが腹圧です
からだを内側から支える仕組みの中心にあるのが、**腹圧(ふくあつ)**です。
腹圧とは、お腹の中の圧力のことで、
- 横隔膜
- 骨盤底筋群
- 腹横筋
- 多裂筋
といった体幹深部の筋肉が連携することで生まれます。
この腹圧がしっかり働いていると、重力に逆らわず、ブレない姿勢で動くことができるのです。
つまり、腹圧は「姿勢の安定」と「動作の滑らかさ」を両立するパフォーマンスの土台。
にもかかわらず──この腹圧が“使えない状態”になっている人が非常に多いのです。
なぜ腹圧が使えなくなるのか?キーワードは「筋膜の制限」
筋膜とは、筋肉・骨・臓器などを包み、全身を立体的につないでいる組織です。
本来は柔軟に滑り合いながら、身体の協調運動を支えるネットワークとして働きます。
しかし、
- 長時間の同じ姿勢
- 呼吸の浅さ
- ストレスや緊張の蓄積
- 過去のケガや手術
などによって筋膜に癒着・ねじれ・滑走不全が起こると、
体幹の深部筋がうまく動かず、腹圧が発揮できない環境になってしまうのです。
つまり、筋膜の制限が、腹圧という内側の支えを使えなくさせ、姿勢や動作に直接影響を与えるのです。
筋膜を整えると、腹圧が働き出す
「体幹を鍛えるより、まず筋膜を整える」
この考え方が、動作の質を変えるカギになります。
筋膜の滑走性を取り戻すことで、横隔膜や骨盤底筋などの動きが改善し、
自然に腹圧が高まりやすい身体の状態がつくられます。
結果的に──
- 姿勢がラクに保てる
- 呼吸が深くなる
- 力を抜いても動きが軽くなる
という変化が起こり、動作の質=パフォーマンスが根本から変わっていきます。
まとめ:筋膜 → 腹圧 → 姿勢と動作の質へ
姿勢が崩れれば、動作も重くなる。
でもその背景には、筋膜の制限によって腹圧が使えなくなる環境があるかもしれません。
筋膜が滑らかに動き、体幹の深部が連動して働くようになると、
姿勢は自然と安定し、動きもスムーズに変わっていきます。
そしてそれは、からだの“構造”を見直すことからはじまります。
S.I(ストラクチュラル・インテグレーション)という選択
S.I(Structural Integration)は、筋膜のバランスと張力の関係に着目し、
身体全体の構造を最適化するための統合的アプローチです。
- 筋膜の滑走性を回復させ
- 腹圧が働きやすい身体環境をつくり
- 重力下で最も自然な姿勢と動作へと導く
──このプロセスを通じて、「動ける身体」へと再構築していきます。
ただ姿勢を整えるだけでなく、構造からパフォーマンスを変えたい方へ。
それが、S.Iの提供する価値です。
本来の身体を取り戻したい方へ
- 姿勢がすぐ崩れる
- 体幹がうまく使えない
- 動きの質を根本から変えたい
そんな方にこそ、S.Iによる構造的アプローチをおすすめします。
お申し込み
エラー: コンタクトフォームが見つかりません。
